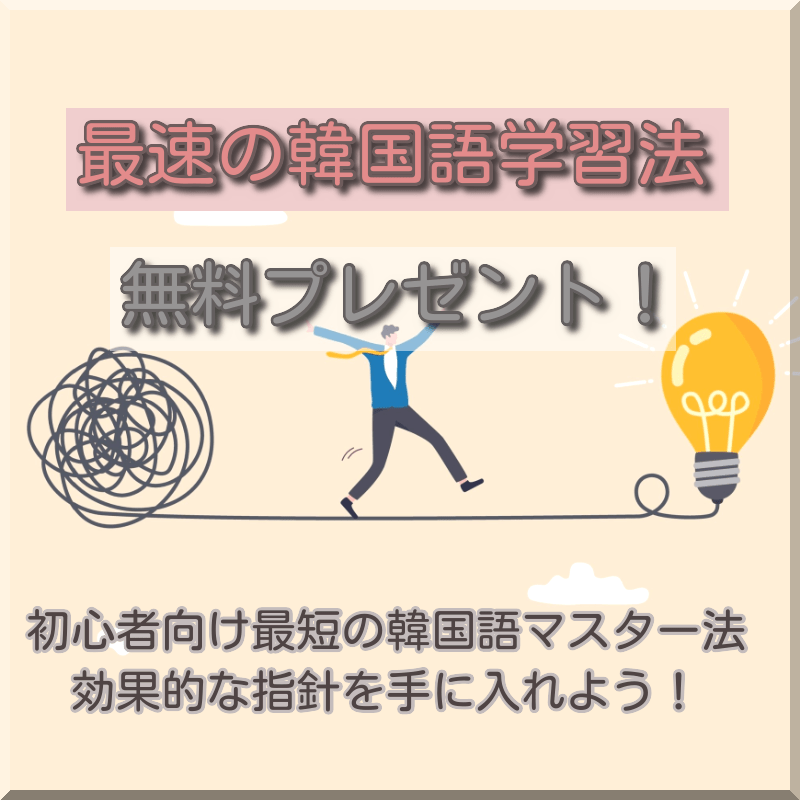目次
韓国ドラマを見ながら韓国語を学んでいる方や、韓国ドラマがきっかけで韓国語を勉強し始めた方も少なくないでしょう。
今回は、時代劇でよく登場する王族に対する名前の呼び方や会話フレーズを紹介します。登場人物の身分がよく分かるようになりますよ。
時代劇で見る韓国の王族の尊称と会話フレーズ
時代劇での陛下・殿下・邸下・王様の呼び方の違い
韓国語では時代劇のことを「사극」といいます。そして王のことを、ある時代劇ドラマでは「폐하:ペハ(陛下)」、またある時代劇ドラマでは「전하:チョナ(殿下)」と呼んでいます。
はたまた「주상전하:チュサンチョナ(主上殿下)」、「저하:チョハ(邸下)」などもあり、様々な呼称が登場します。
「마마:ママ(媽媽:王とその家族に使う敬称)」といった呼び方まで出てきて、初めて韓国の時代劇ドラマを見てmama?と驚く人も多いでしょう。
「韓国の時代劇ドラマはあまり好きじゃない」「好んで見ない」という人がたくさんいます。そういった人は、現代社会を背景としたドラマを好む傾向にあります。それはなぜでしょうか。
一つに、時代劇ドラマの登場人物の名前や呼称が難しいことが挙げられます。日本の時代劇でも「殿」「陛下」「姫」など、固有名詞とは別に王族を呼ぶ呼称がありますよね。
日本人だからこそすぐに覚えられて理解できる登場人物たちですが、これを海外の人が見ると難しさは計り知れません。
韓国の時代劇ドラマでも同じように、日本人に馴染みのない呼称がたくさん登場します。誰が「殿」で誰が「陛下」なのかがわからないと、ドラマのおもしろさは半減しますよね。
これが、韓国の時代劇ドラマを苦手とする日本人が多い理由でしょう。
それでは具体的に、時代劇ドラマではどんな呼び方で王族の偉い人を呼んでいるのでしょうか。実は、背景となる時代によって呼称は様々に変化しています。

権力の差と呼称の変化
朝鮮半島では時代によって王の呼び方が異なりました。ペハ(陛下)は独立国や中国皇室の皇帝を指す言葉で、チョナ(殿下)は従属国や臣下国の王を指す呼び方です。韓国も高麗中期までは「ペハ(陛下)」という呼称を使っていました。
しかし、元の支配を受けていた高麗25代目の忠烈王の時代に、呼称を「皇帝」から「王」に下げて呼ぶようになったのです。
また、朝鮮王朝時代、韓国が明の諸侯国になると、王と後を継ぐ息子の呼称が1段階ずつ下がります。
すなわち「ペハ(陛下)」は「チョナ(殿下)」に、「チョナ(殿下)」は「チョハ(邸下)」に下がったのですね。そして「태자:テジャ(太子)」も「세자:セジャ(世子)」に下がります。
言葉の由来と意味
ペハ(陛下)
ペハ(陛下)という言葉は「宮殿に上がる階段の下」という意味から来ています。「陛」は大変豪華な宮殿の階段という意味をもつ漢字です。韓国の歴史において「陛下」は、王家に対する尊敬の念を表し、王の権威を強調するために用いられました。
中国では、臣下が皇帝に直接ものを言うことはなく、階段の下で護衛する人を通してのみ発言していたことから、皇帝の尊称になりました。現代韓国では、国王や皇后のような存在がいないため「陛下」は使用されなくなっています。
時代劇で「陛下」と呼ばれることが多いのは、王族が登場する場面です。また、王妃や王母などの女性に対しても「陛下」と呼ぶことがあります。
チョナ(殿下)
チョナ(殿下)は「殿閣の下」を指す言葉です。「殿」は高貴な人が住む大きな邸宅という意味をもつ漢字です。
ペハ(陛下)で使われる「陛」が宮殿なので、それよりも下のものということを示しています。殿閣の下にひれ伏す、立って仰ぎ見るという意味ですね。
中国では皇帝にペハ(陛下)という尊称を使いながら、冊封国と呼ばれる従属国の王にもペハ(陛下)という尊称を使うのは、中国皇帝に失礼ということになりました。
そこで、冊封国の王のことはチョナ(殿下)と呼ぶようになりました。
チョハ(邸下)
チョハ(邸下)は王世子、または王世孫の尊称として使われていた名称です。
意味はチョナと違って大きな家を意味する「殿」ではなく、ただの家、つまり「邸」の字を使うことにより、王より低い者という意味を表わしています。
チュサンチョナ(主上殿下)
チュサンチョナ(主上殿下)という呼び方は、高麗の第24代の王である元宗(1259~1274年)の時代以降、モンゴル(元の国)が高麗の王に対して使われるようになります。
娘婿なのだから「皇帝」または「陛下」という呼称を使うのは不適切だとして、高麗の王を「チュサンチョナ」とレベルを下げて呼ぶようになりました(実際は第25代忠烈王の時から「チュサンチョナ」の呼称が使われました)。
ママ(媽媽)
ママ(媽媽)は王とその家族の称号の後に使われ、尊敬の意味を表わす言葉です。特に年配の女性や、自分より年上の女性に対して敬意を表すときに使われます。また、自分の母親や祖母など、親族の女性にも敬意を表すために使用されます。
高官の妾の尊称として使われたり、朝鮮王朝時代に下の人間が尚宮を敬って呼んだりする言葉でもありました。

五方色と服の特徴
朝鮮半島ではその昔、陰陽五行思想に基づいた色彩体系として、五方色(오방색)というものがありました。朝鮮半島の伝統的な色彩体系で、陰陽五行説に基づいているとされています。
この色彩体系は、中国から伝えられた陰陽五行説を朝鮮半島の文化や風土に合わせて解釈したものであり、様々な文化的・宗教的な意味合いを持っていました。
皇帝や王様の服の色にも、この五方色が関連していたと言います。
五方色の意味
東方色:青(청)
東方色は青(청)に対応しています。青は木と関連しており、春の季節とも結びついています。
青は穏やかで清々しく、調和のとれた色とされています。また、自然界で最も広く存在する色であり、天空や海、山々、草木など、多くの自然物に見られる色でもあります。
青は、澄み切った水のように清らかで、同時に、広がりや空間を感じさせる色でもあります。
南方色:赤(적)
南方色は赤(적)に対応しています。赤は火と関連しており、夏の季節とも結びついています。
赤は強いエネルギーや情熱、活力を表す色とされています。また、人間の身体にも似た形をしており、生命力や生命活動を象徴する色でもあります。
赤は、広く使われる色であり、血や赤い花、果物など、多くのものに見られます。
西方色:白(백)
西方色は白(백)に対応しています。白は金属と関連しており、秋の季節とも結びついています。
白は純粋さや清潔さ、誠実さを表す色とされています。また、あらゆる色彩の中で最も明るく、視覚的には最も引き締まった印象を与える色でもあります。
韓服などの伝統的な衣装にもよく使われる色であり、清潔感を与えるためにも多用されました。
北方色:黒(흑)
北方色は黒(흑)に対応しています。黒は水と関連しており、冬の季節とも結びついており、深い神秘性や神聖性を表す色とされています。また、あらゆる色彩の中で最も暗く、不気味さや厳粛さを感じさせる色でもあります。
黒はしばしば哀悼や喪に用いられ、悲しみや不幸の象徴となることもあります。しかし、一方で重厚な印象を与えるため、高貴な身分や力強さを表現する場合にも使われました。
中央色:黄(황)
中央色は黄(황)に対応しています。黄は土と関連しており、夏至や冬至のような太陽の最高点とも結びついています。明るく、暖かく、軽快な印象を与える色とされています。
また、豊かな収穫や成功を表す色でもあります。古代から中国や朝鮮半島で、重要な意味を持つ色とされており、王朝の色としてもよく使われました。
これらの色は、それぞれが持つ特徴や象徴性に基づいて、衣服や装飾品、建物や絵画など、さまざまな場面で広く使われました。
また、五方色は、韓国文化の根源的な色観念のひとつであり、現代の韓国でも、文化的な意味を持つ色として大切にされています。
色による服装の違い
五方色について学んだところで、色による服の違いについて見てみましょう。
皇帝の服:황룡포(ファンニョンポ:黄龍袍)
ドラマ「大祚栄」では中国の皇帝と臣下の服を見ることができますが、中国の皇帝は黄色い服を着ています。五方色の中で最も位の高い色とされていたのが黄色でした。
中国の臣下のうち身分の高い者は、朝鮮の王が着ている服とかなり似た服を着ているのが分かります。
황룡포(ファンニョンポ:黄龍袍)と呼ばれる皇帝の服は黄色で、象徴する霊物は龍です。
王の服:곤룡포(コンニョンポ:袞龍袍)
一方、곤룡포(コンニョンポ:袞龍袍)と呼ばれる王の服は赤で、象徴する霊物は鳳凰です。赤は王や王妃の礼服の色とされていました。当時中国・明の皇帝の服飾品が赤かったことから赤が使われたようです。
身分による服装の違い
李氏朝鮮の時代には、質の良い染料を手に入れることができず、隣の中国より染めた後の布を買っていました。染めた後の布であったため、通常の布よりも高級でした。茶色や藍色などは朝鮮のものが出回っていたともいわれています。
しかし、はっきりとした鮮やかな色が好まれていたため、高貴な人々は高いお金で鮮やかな色の布を入手し、服を作らせていたのです。
一方、庶民は色の付いた華やかな服を着ることが禁止されていました。そもそもそれらの服を用意する金銭的余裕もなかったようです。白や黒の服や、麻の布でできた服を着ている人が多くいました。
韓国ドラマを見ていると、なんとも鮮やかな衣装に身を包んだ美男美女たちを見ることができますが、実際の色はテレビを通して見るほど鮮やかなものではありませんでした。
当時は現在のような染色技術はなかったことから、落ち着いた自然な色合いの服が着られていたといわれています。ドラマで見る色鮮やかで見惚れるような衣装は、現代版の色彩が表れていることに注意が必要です。

歴史の移り変わりと国の独立
韓国の歴史は紀元前2333年に始まります。この時期は「三国時代」と呼ばれ、朝鮮半島を三つに分割されていた時代でした。それぞれの国は、百済、新羅、そして高句麗です。
この時代、高句麗は朝鮮半島北部を支配していましたが、一方で百済は朝鮮半島南部を支配しており、新羅は朝鮮半島東南部を支配していました。
10世紀初めに高麗が建国され、統一された朝鮮半島を支配するようになりました。高麗は、中国との交易を通じて文化や科学技術を取り入れ、発展していきました。
高麗は1392年にイ・ソンゲ(李成桂)が女真族の力を借りて朝鮮を建国し、朝鮮王朝として知られるようになりました。
朝鮮王朝は、この1392年から1897年まで、約500年間にわたって朝鮮半島を支配した王朝となったのです。朝鮮半島の中央に位置し、漢江流域に都を構えたことから、その中心的存在として発展を遂げました。
イ・ソンゲ(李成桂)は、建国後の国土統一、政治の安定化、そして官僚制度の確立に尽力し、朝鮮国家の基礎を築いた偉大なる人物なのです。
韓国の時代劇ドラマに惹かれる理由
韓国語学習者のみなさんの中には「日本の時代劇ドラマはなかなか見ないけれど、韓国の時代劇ドラマは大好き!」という方も多いでしょう。
それは魅力的な俳優陣が揃っているからでしょうか。日本では欠かせない武士が登場しないからでしょうか。それとも、衣装が素敵だからでしょうか。
昔使われていた韓国語や当時の文化を学ぶには欠かせない、韓国の時代劇ドラマの魅力を考えてみましょう。
歴史的な背景
韓国の時代劇ドラマは、様々な時代背景を持っています。王朝時代の衣装や建築、伝統文化などが取り入れられ、歴史的な舞台が設定されています。
現代の日本に生きていたら絶対に味わうことのできない1,000年も前の韓国を体感することができるのは時代劇ドラマ鑑賞の大きな魅力の一つです。
感情的なストーリー
韓国の時代劇ドラマは、しばしば感情的なストーリーで構成されています。主人公たちが愛、友情、裏切りなどの強い感情を経験し、時には戦いながら、物語が進んでいきます。現代の日常とは全く異なる苦悩や困難を垣間見ることができます。
女性が男性の役をするような非現実的な設定がある場合もあり、現実から逃れてまるでファンタジーの世界に迷い込んだかのような時間を過ごすことができます。
アクション
韓国の時代劇ドラマには、アクションシーンがつきものです。刀剣や弓矢を使った戦闘シーンが描かれることがあります。
こちらは日本の時代劇とも重なる部分がありますね。忍者のように宙を舞う躍動感ある演出が登場する場合もあり、見どころの一つです。
美しい映像
韓国の時代劇ドラマは、旅行では回り切ることのできない韓国の美しい映像が特徴的です。
王宮や広大な山々、民家の様子まで、建築物の美しさが映え、視覚的に楽しめます。日本とは全く違う街並みに、まるで旅行に行った気分で鑑賞できるのもポイントです。
文化的な背景
韓国の時代劇ドラマは、韓国の文化的な背景や当時の様子を反映しています。伝統的な儀式や料理、音楽などが描かれ、ドラマを見るだけでかつての韓国文化を知ることができます。
韓国人に「そんな昔のこと、なんで知っているの?」と驚かれるかもしれません。
強い女性キャラクター
韓国の時代劇ドラマには、性格の強い女性キャラクターが登場することが多いです。彼女たちは、男性たちと対等に戦い、活躍する姿が描かれます。
日本の時代劇ドラマにはおしとやかな女性が登場することが多いでしょう。これも韓国の時代劇ドラマとの大きな違いです。
かつての尊称や服装について詳しくなったところで、改めて時代劇ドラマを見てみると、これまでとは違った観点からストーリーに入り込むことができるかもしれません。
それでは、昔の言葉はどのようなものが使われるのでしょうか。

時代劇の中でよく登場するフレーズ
登場人物の呼び方や歴史について学んだら、最後に時代劇でよく使われるフレーズについて学習しましょう。
これを覚えれば、様々な時代劇でその次代特有の話し方が理解できるようになりますよ。字幕を見ないで鑑賞できる日も近いかもしれません。
当時は「~でございます」という意味の文末表現「옵니다(オムニダ)」をよく使っていました。これは「옵나이다(オムナイダ)」を省略した形で、こちらの方がより丁寧な言い回しです。
송구하옵니다
恐れ入ります、申し訳ございません
王様に家来が怒られるシーンでよく登場します。
망극하옵니다
大変光栄でございます
王様に家来が褒められるシーンで、家来が発言しているでしょう。
その他にも、下記の通り時代劇で登場する多くのフレーズがあります。今みなさんが学習している韓国語は現代語のため、中級以上のレベルが身についていても、これらのフレーズを知らなければ意味を理解することができません。
【文末が「옵니다(オムニダ)」となるもの】
황공하옵나이다
恐れ多きことでございます
당치 않사옵니다
とんでもないことでございます
성은이 망극하옵니다
有難き幸せでございます
잘 모르옵니다
存じ上げません
물러가겠사옵니다
下がらせていただきます
명심하겠사옵니다
肝に銘じます
그러하옵니다
さようでございます
【文末が「옵니다(オムニダ)」とならないもの】
통촉하여 주시옵소서
お聞き入れくださいませ
부르셨습니까
お呼びでしょうか
이리 오너라
こちらへ来なさい
안으로 드시지요
中へ入りなさい
뫼시어라
お連れしなさい
거기 앉거라
お座りなさい
들어오너라
誰かおらぬか(※お入りなさいでも使用される)
밖에 있는가?
誰か(外に)おらぬか?
드려보거라
申してみよ
주상전하납시오
王様のお出ましです
これらの言葉がドラマの中に出てきても、聞き取りすぐに意味を理解することは難しいでしょう。聞き取れるようになったら時代劇の中に入り込んでも会話ができるかもしれませんよ。
まとめ
韓国の時代劇ドラマをキーに、当時の王族の尊称や使われていたフレーズを学んできました。
時代劇ドラマを見たことがない人には、馴染みがなく少し難しい内容だったかもしれません。また、現在の日常生活であまり出てくる言葉ではないので、不思議に感じることが多かったかもしれません。
しかし、勉強する中で現代の表現と過去の表現を一緒に学ぶと、言葉の変化を見ることができてより勉強が楽しくなるはずです。これをきっかけに、韓国の様々な文化や言葉のルーツなどにも目を向けてみてくださいね。